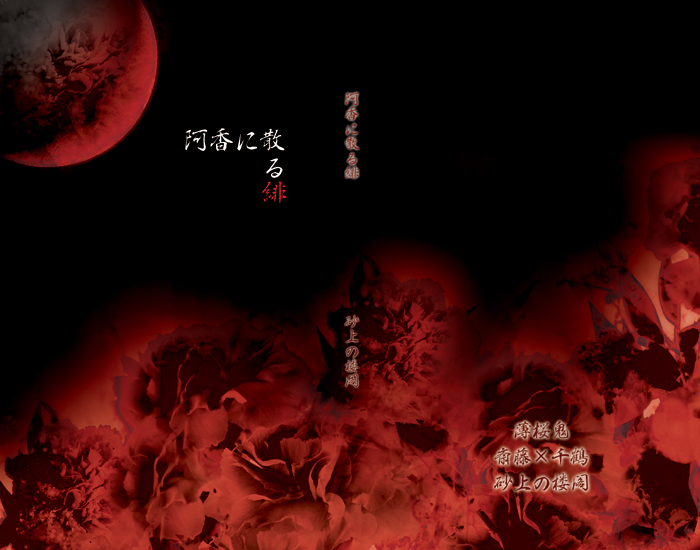本文 序章&一章抜粋
それは、破滅へ誘う華。
艶やかにに咲き誇れば咲き誇るほど匂い立ち、
その甘い香りで、強靱な心さえ惑わし狂わせる。
甘い香りが辺りに漂う。
梅の香のようであり、薔薇の香のようでもあり、百合の花の香のようでもある。
優しくまとわりつき、ゆっくりと浸透してゆく。
ふわり・・・ふわり・・・
人気もまばらな薄暗い神社の裏道だというのに、まるで百花繚乱の花園に紛れ込んだと思わせるほど甘い香りが充満していた。
赤く色づいた葉は風に吹かれ落ち、丸裸になった枝がただ伸びるばかりだというのに、極楽浄土もかくやと言わんばかりに、甘い香りが漂う。
華の蜜を濃縮したかのように。
人気の皆無となった夜道を男は一人で歩いていた。
たったいま手に入れたばかりの煙管を手に持ち、時折口に運びながら煙を吸い込む。
ふわり・・・酒を呑んだように心地よい酩酊感がじわりと身体中に広がってゆく。
甘い蜜の薫りは胸ヤケを起こしてもおかしくないほど濃蜜だったが、不思議とその甘さが心地よい。
酒を呑むより遙かに心地よく、男は久方ぶりに顔に笑みを浮かべる。
この一年半苛んでいた苛立ちも、鬱憤も、すべてが蜜にとかされて消えてゆくようだ。
まだ自分はやれる。
一度は喪失しかけた自信が沸々とわいてくる。
「ああ・・・できるさ。わし自身は何も不始末はやってないんだからな」
自分自身に落ち度があったのなら、今もまだ組長という肩書きを背負うことを許されていないはずだ。だが、自分は今もまだ組長の看板を背負うことを許されている。それが答えだ。
まだ、灯火は消えていない。
男はうつろな眼差しに、野心の色を浮かべると煙管に視線を落とす。
これを手に入れたのは偶然だった。
いや、偶然ではない。きっと必然だ。
普段は通らない道をたまたま気まぐれで通った時、薄汚れた流民が声をかけてきたのだ。
「お武家様、お一ついかがですか 」
流民はいきなり煙管をつきだしてきた。
どこに出もあるような安い煙管。
男は眉をひそめてそれを振り払う。
流民ごときから施しを受けるほど落ちぶれてはいない。それどころか、流民にまで哀れみを受けた事に腹が立ち、男は腰に差している刀に手をかける。
「そう、いらだたないでください 一服して落ち着きませんか?」
流民は煙管を口にくわえて煙を吸い込むと、こともあろうことかその煙を男に吹きかける。
「きさま、無礼にも程がある!」
怒りに顔を赤く染め男は刀を抜きかけたが、その前に甘い蜜のような香が身体の中に浸透していき、手が思わず刀から離れる。
男は気がついていなかったが、鼻がひくひくと動き煙を追うように顔を動かす。
その様子をじっと監察しながら、流民は再度煙を吸い込むと、ゆっくりと吐き出す。
甘い蜜のような芳醇な香を
「とてもよい香でしょう。これは身体の疲れをとり、活力を生み出してくれる特別な薬なんですよ」
流民は懐から薬包を一つ取り出し、それを広げてみせ、白い小麦粉のような粉を見せる。
「特別な薬? なぜお前のような輩が薬など高価な物を手にしている」
どこからか盗んだ物を高く売りつけようとしているのだろうか。貧しい身なりをした流民が持つような物ではない。
「これは、私の家系に先祖代々伝わる秘薬 材料は特別効果なものではないので、ご心配しているような類の薬ではないんですよ」
唇からゆっくりと紫煙が吐き出され、煙はすぐに夜陰に消えてゆく。だが、甘い香りだけはいつまでもその場に止まり、荒れようとする心を静める。
「お前、江戸から流れてきたのか?」
上方の発音とは違う言葉を使う流民を男はうさんくさそうな視線を向ける。江戸からわざわざきな臭くなり始めている、京の都へ流れてきたというのだろうか。
「僕は違います」
ぼくは・・・とはまた妙な言い回しをする。
胡散臭げに男が見下ろしていると、流民はかすかに口元に笑みを浮かべたようだが、もっさりとした髪が流民の顔を覆っているため、表情ははっきりと見えない。
「生まれ故郷は陸奥なんですよが、生き別れの妹が江戸にいると聞いています。その妹が京へ来ていると噂で耳にしたので、僕も京へ来たんです」
流民にしては言葉遣いがやたらと綺麗だ。それなりの家に生まれたものの、家が取りつぶしにでもあったのか この流民の目的がようとしてしれない。
「なぜわしに声をかけた」
「お武家様のお顔に疲労の影が浮いてましたので。失礼かと思いましたが、気付け代わりになればと」
再び、ふわりと甘い香りが男の鼻先をくすぐる。
そんなものはいらない。と突っぱねようと思うのだが、この甘い香りを嗅いでいるとどうしても欲しくなってくる。
その欲求を示すかのように目が徐々に物欲しそうな物へとかわり、喉が露骨なまでに音を立てて鳴り、舌が厚ぼったい唇を舐め上げる。
男は無意識のうちに渇望していた。
甘い・・・蜜のような香を直に身体に取り入れる事を。
「吸ってみますか? お武家様」
差し出された煙管を男は拒絶しようとした。
流民が口にした物を手に取るのは、武士としての矜持が許さない。
だが、欲しい・・・どうしても直に肺にいれてみたい。
この蜜のような香を肺に取り入れたらどんなに至福の瞬間を味わえるのか。
男は糸で引かれるように手を伸ばし煙管を手にする。
口を付けるのにためらいが無かったとは言えないが、男は口にくわえゆっくりと煙を吸い込む。
煙管を吸うのは初めてではない。幾度か吸ったがどうも煙くて好きになれなかった。
だが、この煙はまったく別物だった。
男は恍惚の表情を浮かべながら、一呼吸・・・二呼吸と煙を吸ってゆく。肺に煙が満ちるたびに、血管を通って蜜が身体をゆるりと巡る。
「お気に召して頂けましたか」
流民の問いに、男は満足そうな笑みを浮かべて頷き返す。
流民に対する警戒心はすでに存在しなかった。
この流民がどこの誰で、何のために自分に声をかけたかなどもうどうでもいい問題だった。
この不思議な甘い蜜を自分が受け取るための天啓だったのだ。それを肯定するかのように、流民はそれを差し上げましょうと言ってきたが、男はこれだけでは物足りなかった。
もっと欲しい。貪欲までに強い欲求が湧いてくる。
「もっとないのか? これだけではすぐに吸い終わってしまう」
火皿を見ればもう半分が燃えつきていた。これではすぐに全てが灰に変わり、至福の時間が終わってしまう。
今だけではない。明日も明後日もずっとずっと、幾度も吸っていたかった。
「ここに十日分あります」
流民はことさらゆっくりと懐に手を忍ばせると、薬包を十包取り出すと、男はむしり取るように流民から受け取る。
「一日の限度は一包になります。依存性の強いものなので量は守ってください。十日毎にこちらにいますので、入り用でしたら声をかけてください」
流民はそれだけを言い残すと闇に消えるように、神社の奥の林の方へ去ってゆく。
その後ろ姿を見送ると、男は周囲に人がいないことを確認し、そそくさとその場を去る。
新選組組長の一人が流民から物をもらったところを見られたら、どんな噂が立つか。
運がいいことに人通りは皆無と言っていいほどなく寂れた道だ。
誰の目にもつくことはなく、男は愛妾の待つ別宅へと急ぐ。
ふわり・・・ふわり・・・
甘い匂いがつきまとう。
肌に、手に、髪に。
極上の酒をあおるよりも心地よい酩酊感は至上の喜び。
「一滴の墨を投下したよ。さて、どのぐらい、清き水を汚してくれるのかな?」
流民は穏やかな表情には似合わない、酷薄な笑みを口元に浮かべ、千鳥足となってゆく男の後ろ姿を凝視していた。
一、
『薬・・・薬をくれ・・・・っっ!!』
その男は突如何の前触れもなく、戸を蹴り破って診療所に押し入ってきた。
父の手伝いをして包帯を患者の足に巻き付けていた千鶴は目を見開いて、乱入してきた男へと視線を向ける。
千鶴だけではない、待合室で待っていた患者達も、診察途中の患者も誰もが呆気にとられていた。
だが、男はそんな事に構う様子は一切無かった。
濁った目で綱道を見定めると、ふらついた足取りで近づいてくる。
酒にでも酔っているのかその足取りは酷く不安定で、何もないところで蹴躓いてひっくり返ったり、棚や台にぶつかったり、真っ直ぐ歩けない様子だった。
千鶴はとっさに立ち上がって駆け寄ろうとするが、それを綱道は抑える。
『いてぇんだ。体中痛くて痛くてたまんねぇんだよ! お願いだ、先生、痛み止めをくれ!! もう、ねぇんだよ!!』
男はまるで餓鬼のようだった。
目は落ちくぼんでぎょろりとし、頬の肉は痩け骨に皮膚が張り付いているようにしかみえない。頬だけではない体中の肉がこそげ落ち、骨と皮しかなく、着物の合わせ目から見える胸元は洗濯板のように肋骨が浮いていた。にも関わらず腹は膨れあがり、カサカサになった肌は黄色みが強くでている。
病魔に冒されていることは一目瞭然だった・・・男は肝を病み、その痛みに苛まれていた。
『あれは、中毒性の強い薬だと言ったはずだ。規定量を守ってなかったな』
綱道の厳しい表情にも男はひるむことが無く、一歩・・・また一歩と近づいてくる。
『規定量じゃきかねえんだよ。お願いだ、先生、助けてくれ、いてぇんだよ。体中痛くて痛くてたまんねえんだよ!!』
胸が痛くなるような悲痛な叫びが響く。
やせ細った身体の何処にそんな声を出す力があるのかと思うほど、その声は人々の胸を痛くした。
たっつぁんは、不治の病だろう?
ああ、酒の飲み過ぎでやっちまったらしいぜ
浴びるように若い頃から呑んでたからなぁ
なんで、腹だけがあんなに膨れてるんだ? 身体はあんなに痩せて骨と皮だけになってんのによ。
腹に水がたまっちまってるんだと。肝をやると水が腹に溜まるらしい。
相当いてえらしいな。綱道先生が出した痛み止めって副作用が強いんだろ?
らしいな。おたまの所のかかぁがお侍に斬られて死にかけた時、苦痛を紛らわすために使ったって聞いたことがあるぜ。回復の見込みのない患者にしかつかわねえって話だよ。
死ぬまで痛みに苦しまなくてもすむならありがてえけどよ、そんな薬使うような病にだきゃあなりたくねえな。
ああ、あんな風になりたかねえや
患者達がひそひそと話す声が聞こえてくる。
彼らは皆顔なじみだ。今痛みを訴えるのが何処の誰で、どんな病気を患っているのか綱道が話すまでもなく知っていた。
もうまともに起きあがる体力すらなく、死を待つばかりの寝たきりだったという事まで。
『これ以上の処方は、あんたの身体を死に追いつめる』
『先生、あっしはもう死ぬんだ。今更幾日生き延びたって苦痛に苦しむだけなんだ。お願いだ。薬を 薬をくれ!! 苦しみ藻掻いて死ぬことだけはいやだっっっ!!』
男の悲痛な叫び声に誰もが目を伏せる。
男の死期が近いのは誰が見ても一目瞭然だった。治療法もなくただ息絶えるのを待つばかりと言っても過言ではないほど、死相が男には出ていた。医者で無くても誰が見てもそれは明らかなほどに。
『せん・・・・・・・げふぉっっっ』
男はよろめきながら綱道にすがりつこうとするが、その途中で黒い血を吐き出す。
それは、人が流す血とは思えないほど黒く、腐臭のような臭いを放ち、男の口から溢れてボタボタと滴り落ちる。
『皆、悪いが後日出直してくれ』
綱道は男を支えながら、待合所にいる患者達に声を掛ける。
誰もが青い顔をしながら頷き返し、そそくさとばかりに飛び出して行く。
男は細い息をして今にも息絶えそうだったが、それでも強い視線で綱道を見上げていた。
『先生・・・お願いだ・・・薬 薬を お願いだ!!』
男の最後の力を振り絞った叫び声に、千鶴は見ていられず目を背けてしまう。手伝いをする以上、患者からは目を背けてはいけない。そう教えられていたが、どうしても正視することが出来なかった。
知らず内に握り締めていた手がふるふると震えていることに綱道は気がついていたが、何も気がついていないかのように千鶴に指示を出す。
『千鶴、阿香(あこう)を調合してくれ 濃度は1.5倍に』
『父様!?』
それは強すぎるのではないだろうか。
あれは、効果が強すぎる故に調合は慎重に慎重を重ねなければならないと、耳が痛くなるほど言っていたのは綱道自身だ。
『この者には適量では効かん。千鶴、出来るか?』
綱道の問いに青い顔をしながらも頷き返す。
これから調合する薬は、確実に男を死へと誘(いざな)う。
その薬を今から自分が作るのかと思うと、身体の震えも涙も止まらなかった。
秤に薬を乗せて計量をしようと思っているのに、震えている手では秤の上に薬剤を上手く載せる事ができず、ポロポロとこぼれ落ちてゆく。
その様子を見ていた綱道は何も言わずに、千鶴から道具を取り調合を始めた。
黙々と作業をする綱道を見て、千鶴は昔幾度も言われてきた言葉を思い出す。
『千鶴、薬は人を生かすことも、殺すことも出来るんだ。だから、調合は慎重にせねばならんよ』
初めて薬を触ったのはいくつぐらいの頃のことだろうか。
まだ、ずいぶん幼かったと思う。
父が乳鉢ですりつぶしているのを脇で見ていると、父は穏やかな笑顔を浮かべながらも、一言一言千鶴が聞き逃さないように教えてくれた。
どんな薬でも、調合を間違えば人の命を奪ってしまう毒にもなりえる。
見方を変えれば、毒は使い方次第で薬にもなると言うことだ。
そう言った類の薬草が、診療所の薬棚にはあいくつもあった。
その一つ一つの効能を、父は丁寧に教えてくれた。
毒としての役割と。
薬としての役割を。
『父様、何を作っているの?』
種のようなものを丁寧にすりつぶして細かい粉にした物を煮立たせ濃縮しているのを見ながら、千鶴は首を傾げる。
父は顔の下半分を大きな布で覆っていた。
その姿はまるで大晦日に大掃除をするときのようだと幼心に思う。
『これは、痛みをなくす薬だよ・・・ああ、千鶴。これは身体に良い物ではないから、近づいてはダメだよ』
『身体に良くないものなら、毒なの ?』
大好きな父親に駆け寄りかけた千鶴は足を止め、出入り口の所からひょっこり顔だけを覗かせて問う。
辺りには微かに甘い匂いが漂っており、とても毒のようには思えなかった。
『使い方次第では、これは人を滅ぼす毒になるね。でも、今父様は苦しんでいる人を助けるために作っているんだよ。だから、怯えなくても大丈夫だ。ただ、これは小さなお前には強すぎるからね・・・さぁ、外で遊んでおいで』
それが、何の薬なのか知ったのかはもう少し大人になってからのことだ。
痛みを取ることの出来る不思議な薬。
甘い・・・甘い香りを放つ薬。
『お前にも教えておこう。だが、他言してはならないよ? これは、雪村家が先祖から受け継いできた秘中の秘薬なのだからね。そして、使い方を間違えるのではないよ。お前の身すら滅ぼしてしまいかねない、毒薬でもあるのだからね』
どんな毒素を含む薬草を扱っていても、ここまで注意をしたことはなかった。
ただ、父は繰り返し言う。
それは、人を狂わす毒だと。
『父様、この薬の名前は何?』
白い粉を水に溶かしそれを患者に服用させると、痛みにのたうち回っていた患者が徐々に穏やかな表情を浮かべ、まどろみの中を彷徨うようになる。
あまりにも毒性が強いため、気が狂わんばかりの痛みに苦しむ患者にしか使えない薬。
その効能を目の当たりにし、千鶴はなぜかわけが判らない恐怖に身体が震えた。
目の前の患者は馬に足を踏みつぶされて、足の形をすでになくしていた。膝から下を切断する以外に治療の手段はない。だが、足を切ってその後の処置をする間の激痛に耐えられる人間がいるはずがない。
『父様は、阿香(あこう)と呼んでいるよ』
苦しみをつかの間忘れさせるために、父は阿香と呼んでいる薬を使っていたのだが、想像を絶する痛みを忘れさせる薬を目の前にして、千鶴はただ怖かった。
患者が恍惚とした表情で横たわっているその姿が異常に思えて
その薬を綱道は、死期を迎えようとする患者に投与していた。
そして、今目の前で一人の男が苦痛を忘れまどろみの中をたゆたう。
死への旅路に出る・・・その時まで。
男は夢の中にいるように、目は虚ろで唇はだらしなく開き、微かに笑みの形を作っているように見える。彼にとっては全身を苛んでいた苦痛から解放されて、ようやく安息の時間を手に入れられたのだろうが、強すぎる薬は確実に彼から生きる力を奪い取っていた。
苦痛から逃れられ、細くなってゆく息を見つめながら、千鶴は震えを止める事が最後まで出来なかった。