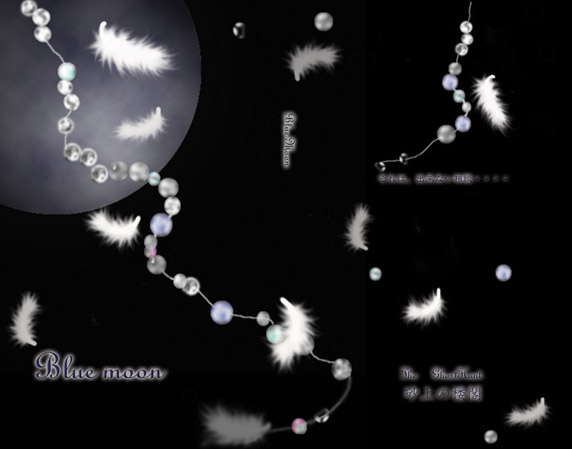本文 序章抜粋
どんよりとした暗い色の雲が空を埋め尽くす。ここ数日の間一度も晴れ間を見せることなく、シトシトと冷たい雨が降り続いていた。
傘をさしていても、霧雨のような冷たい雨は風に流れ、髪や衣服をしっとりと濡らし、体温を奪い傘を持つ手がかじかむほど冷たくなってゆく。
連日のように雨が降り続いているせいか、週末の繁華街といえど人通りが少なく、路地を一本奥に入れば尚更もの悲しい雰囲気を醸し出していた。
カツカツカツカツ
傘が激しく上下し、髪やコートが水気を含むのを気にすることなく、濡れた路面の上を走るように急いで歩いていく。
時間を気にしているのか、幾度も視線は腕へと向けられていた。
今日こそ来てくれるかもしれない。
期待に胸を膨らませて、今にも駆け出さんばかりの勢いでひたすら歩いていく。
『ずいぶん待たせて悪かった』
照れているような、少し困っているような笑みを浮かべながら、顔を合わせるなり彼は謝罪の言葉を口にしながら来てくれるかもしれない。
約束の時間まであと僅か。
紹介してくれたお店で会おうと約束しても、その約束が果たされなくなって今日で何度目になるだろう。
時間を過ぎても来ない彼にメールを送ると『仕事が終わらない。今日は行けそうにもない』いつも同じメールが届く。
そのメールに意気消沈していると、必ず二通目がすぐに届く。
『今日は無理だけれど、明日なら何とかなる』
と。
仕事だから仕方ない。
自動車の設計部に在籍し、昼夜ともなく仕事に追われていると以前言っていたのだから、気楽なOLをやっている自分と違って、定時に上がるなんて事が出来るわけがない。
残業どころか、毎晩毎晩最終電車で帰るか、会社に幾日も泊まり込むような生活をしているのだから、会えることの方がまれなのは仕方ない。
『私はいつもの時間にはバーに居るから、来れるときが来たら来て。でも、無理はしないでね』
女はいつもおきまりのメールを返信する。
どんなタイミングで彼に時間が出来るのか判らないから、いつ急に来ても大丈夫なように、毎晩毎晩、すっかり行きつけと化したバーへと足を運ぶ。
もしかしたら、今日こそ彼は来れるかもしれない。
忙しいのに時間を作って来てくれていたのに、待たせてしまったら申し訳ない。
だから、時間前にはいつものバーに入っていたかったのに、こんな時に限って仕事をギリギリに頼まれ、普段はない残業をする羽目になってしまった。
こういう時に限って、タイミングが悪いことに彼が来ていたりするかもしれない。そう思うと気ばかりが急いて、泥がはねるのも気にすることなく女は急ぐ。
それでも急いで駆けつけたかいがあって、時間までには店にたどり着く。
「いらっしゃいませ。いつもので宜しいですか?」
女が姿を見せると、カウンターの中に居たマスターの方から声を掛けてくる。
女は息を切らせながら周囲に視線を向けて、待ち人がすでに来ているか狭い店内をすぐに確認するが、そこには求める姿はまだ無かった。
まだ、時間は早い・・・きっと、一杯ぐらい飲んでいる間に、彼は来てくれるはず。
そう信じて、女はすっかりと定位置となっている、カウンター前のイスに腰を下ろし、マスターに「いつもの」とボソボソとした聞き取りづらい声で告げた。
女は一人グラスを傾け続ける。
静かな店。人々のざわめきはほとんどなく、交わされる声もどこか潜めいたもの。いつも座っている席に、この日も一人で座る。
毎日・・・毎日同じ場所に。
絶えることなく繰り返された一年。
聞こえるのは静謐な音を響かせるピアノの演奏と、バーテンダーが振るシェイカーの音。
誰も、自分のことなど知らない。
誰も、話しかけてなどこない。
ヴァイオレット色をした透き通った液体を傾けながら、思わず笑みをもらす。
掠れた声は誰の耳にも届かずひっそりと消えてゆく。
この声のように、自分の事も消えて行くのだ。
皆の記憶からも、あの人の記憶からも・・・
誰も自分のことなど覚えていてはくれないのだ。
忘却を食い止める事は不可能な事・・・・・・
皆自分に都合の悪い事は忘れていくのに、どうして自分だけは忘れられないんだろう・・・・・・
繰り返したくなくて、次こそは・・・と思っていたのに、気がつけばまた同じ。
今度こそ大丈夫だと思ったのに。
信じても平気だと、人を裏切るような人ではないと思ったのに・・・・・・彼は今日も来ない。
今日こそは来てくれる。
明日はきっと来てくれるだろう。今日は彼の仕事が忙しくて無理だったんだ・・・
今日こそ・・・いや明日こそ・・・やっぱり今日こそ・・・明日こそ・・・気がつけば約束の日から、一年が経とうとしているのに、諦めがつかず毎日毎日バカみたいに通い続けることを止められずにいた。
いいかげん、見限りをつければいい。所詮はその程度の男だったと。ただ単に自分の人を見る目がなかっただけなのだから。
思いっきり我を無くすぐらい酒を飲んで、泣き叫べばいい・・・・今までしてきたように。
なのに、できない。
あの人だと思ったから。
彼なら大丈夫だと思ったから。だから、信じたのに・・・
「ブルー・ムーンを」
バーテンダーに向かって掠れた声で呟く。
酒に焼けたようなだみ声。もう顔は真っ赤になり、目はどことなく虚ろ。グラスを持つ手も危うげなものがあるが、バーテンダーは彼女を止めることはせず「かしこまりました」と、丁寧な口調で応じた後、シェイカーにリキュールなどを入れて初めはゆっくりと・・・だが、手際よくリズミカルに振る。
そして、新しいグラスに注がれたた『ブルー・ムーン』と言う名のカクテルが目の前に静かに置かれる。直訳をすれば『青い月』だが、そこに込められた言葉は《出来ない相談》
美しいヴァイオレットの色を纏ったカクテルだが、そこに込められた意味は無情な物だった。
まさに、冷たい青い色を称えた月の名を与えられたと言うべきだろうか。
女は目の前に置かれたグラスに手を伸ばす煽るように一気に飲み干す。
口当たりはすっきりとしているが、アルコール度はけして低くはない。飲み干した瞬間胃がきゅっと熱を持つ。
グラスを目の前に戻すと、女は崩れるようにカウンターの上に突っ伏し、空になったグラスをぼんやりと見つめる。
永遠に覚えておくことなどけしてありえない・・・・人は忘れることが出来る生き物。
どんな約束でさえも人は忘れることが出来る。
どうすれば忘れない? と誰に聞いたとしても無理なことだ。
よほどの事がない限り忘れて行くのだ。
自分と言う女の存在も彼の中では当の昔に忘れ去られているのだろう。都合のいい女と言うフォルダーにしまわれ、そのうち削除されてしまうのだ。
あってもなくてもどうでもいいフォルダーに納められているファイルの一つのように、簡単に削除できる程度の記憶。
彼の記憶に留めておく事は不可能な事・・・・なら、それを可能にするには?
答えがでないまま女は、答を求めて毎日待ち合わせの約束をした店へと足を運び続ける。
未だ来ない待ち人を待つために・・・・・・・・・