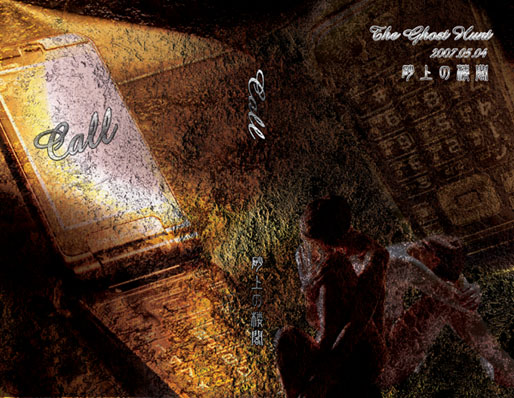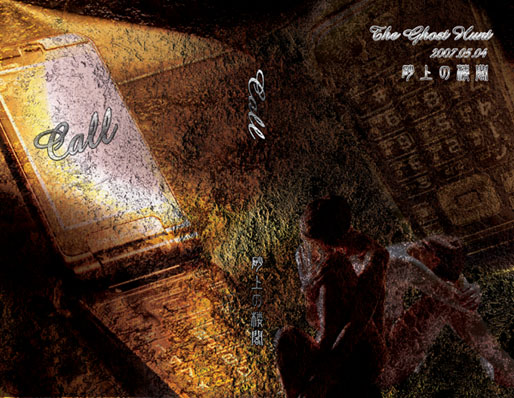序章より抜粋
夜が徐々に深まりつつある。
通りを照らすほのかな灯りは、地上に真の闇を近づけさせない。暗闇を打ち払うかのように、赤く、青く、黄色く輝くネオンにより昼間の如き明るさを保っている、賑わいという名の雑音を抱えながら。
ざわめきは騒音となり、隣を誰が通り過ぎたのか、どんな会話をしていたのか気にもとめる者ど誰もいない。
若年層が多く集っているため制御を欠いた街、渋谷。品性の欠片もなく、アスファルトの上に直接腰を下ろし、目的もなくただそこに座って話し込む子供達が溢れ、声たかだかに言葉を交わす。
学生鞄からタバコを取り出し紫煙を吐き出す姿を見ても、眉を潜める者すら居ない街。
美観に優れ治安がいいとはお世辞でも言えない。だが、ほんの少し道を変えれば、閑静な住宅街が広がり、高級住宅地と呼ばれるエリアへと移りゆく。
喧噪は遠くに潰え、瀟洒な住宅がならび、高級車が当たり前のように駐車している光景に。
どの家々も、綺麗に整えられた生け垣に囲まれ、敷地内の様子を通りから伺い知ることは出来ないが、家族が集って居るであろうリビングから、柔らかな光が漏れていることだけは、生け垣の隙間からも伺うことはできた。
その中で一箇所だけ異質な空間があった。
広々とした庭には腰ぐらいまで届きそうな雑草が生い茂っており、長い年月人の手が入っていないことを臭わせる。
周囲と隔絶するための生け垣もはた迷惑なほど伸び、歩道へと枝を伸ばし通行する人々の歩行妨害となしていた。
生け垣と荒れた庭の奥に、ひっそりと佇む洋館も庭や生け垣同様荒れたイメージを通りすがりの人間に与える。
煉瓦壁にはびっしりと蔓草が生い茂り、窓さえも塗りつぶしてしまいかねないほど伸びた枝は、電線を伝って電柱にまで達しようとしていた。
風雨にさらされ赤く錆びた門といい、長い年月誰も開閉していないことを知らしめる。
通りすがりの人間がこの家を見たのならば、幽霊屋敷と思っても仕方ない様相。
その有様に近所に住まう人間すら薄気味悪く感じていた。
いや、近所に住むからこそ感じてしまう。
誰が最初に気がついたのかそれすらも定かではないのだが、ふと気がつけばこの家の住人の姿をパタリと見なくなった。
夜逃げでもしたのだろうか。誰ともなく呟く。
けして珍しくはない。
事業を失敗し倒産した家の者は、人目を忍ぶように真夜中に出ていく。
何度も目撃したことのある光景だ。
見て見ぬふり・・・気がついても知らぬぞんぜぬを繰り返す。誰が訪ね問いかけてこようとも。
だが、誰も夜逃げをするところを視た者は居ない。
日中に引っ越しをするところも見ていない。
この家に借金取りが押し寄せてきた所を視た者もなく、一つの財産となる家屋や土地も転売されることなく、静に寂れていく。
陰湿な雰囲気を保ちながら。
とぅるるるるるる・・・・
とぅるるるるるる・・・・・・・・・・・・
微かな電話の音が空気を震わせる。
どこからか聞こえてくるのか、微かな小さな音。
その音と同時に、暗闇の室内に青白い光が灯る。
人の気配などないというのに、微かな・・・音量に負けてしまいそうなほど小さな、絞り出すような声が漏れ出る。
「誰か・・・・助けて」
少女はひび割れた声で呟いた。
ただ一つ、時折青いランプを灯す電話機一台がある部屋に。
この日も、それはいつもと同じ時間に無機質なコールを響かせる。
とぅるるるるるる・・・・
闇の中に灯る青白い光に照らされて、顔が浮かび上がる。
頬の肉が全てそげ落ち、肌はかさつき白く粉を吹き、唇は乾涸らびて皹が入り血を滲ませ、力をなくした虚ろな双眸をした老婆のような容貌の少女固い木の床に寝っ転がっていた。
彼女は舌先で唇を湿らせようとするが、乾涸らびた口腔内には唾液などなく、唇を湿らせることはできない。
それでも、反射的に唇を舐める。
枯れ枝のような腕に力を込めるが、微かに指先が動いただけで腕はピクリとも動かない。
浅く呼気を繰り返しながら、電話を凝視し続ける。
虚ろな眼差しに、それでも恐怖を滲ませながら。
「な・・・んで 」
渾身の・・・なけなしの力を振り絞って右腕を伸ばすと、無機質な電話の音に混ざるように、じゃらりと重い音が発せられる。
「どう して 」
乾涸らびた喉で無理矢理声を出しているせいか、激しい痛みに襲われるが、もう涙を流すだけの水分が体には残っていなかった。
今にも命の灯火がつきようとしている少女とは正反対に、電話は己の役目を果たすべく音を鳴らし続ける。
「ど・・・して 」
弱り征く声は、恐怖の色に染まる。
それは、もう鳴らないはずだった。
己の役目を全うできなくなっているはずだ。
誰が見ても、それはもう動くはずはないと応えるだろう。
常識で考えれば。
「な・・・んで、鳴る の っっっっ」
己を生かすための力も、生を望む希望もなくした顔に、ただ恐怖だけが滲む。
まっぷたつに折れてなお、着信をしらせる電話を見つめながら。
とぅるるるるるる・・・・
とぅるるるるるる・・・・・・・・・・・・
少女の恐怖など知るよしもなく、電話は、永遠に鳴り響く。
切られる事もなければ、留守電に切り替わることもなく、少女が手に取り通話を押すまで永遠に鳴り響く。
少女は虚ろな眼差しで、青白く光る電話を見つめ、無機質な音を聞き続ける。
もう、何日も・・・何週間も・・・いつから始まり、いつ終わるのか判らない日々を、ただそれを見て聞くだけで過ごしていた。
鳴るたびに受話器を取り、切ってもまた鳴る電話をまっぷたつに折るその時まで続いていた・・・
もう終わるはずだった。
二つに折ったその瞬間に、全てが終わるはずだった・・・幕を己の手で下ろしたと思ったのに・・・・
「なんで、まだ 鳴るの?」
終わって欲しい。
もう、電話の灯りも、着信音も聞きたくはない。
それが壊れることによって、外との連絡方法が潰えてしまっとしても、永遠に音を聞かされ続けることよりマシだった。
なのに、終わりは来ない。
永遠に続く。
果て無く。
少女が望んだ終わりを告げる事は無かった。
「うそ、なんでこれがこんな所に売ってるの?」
見つけたのは偶然。
だが、本当に偶然だろうか。
そんな疑問を少女は抱くことなく、絶対に手に入れることの出来ないであろう宝物を手に取る。
レジに保っていくと店員が驚いたような顔をするが、なぜそんな顔をするのか少女には理解できない。
見つけた掘り出し物。
なぜ、こんな破格な値段で売っているのか。
『ヤバクネ?』
友人の一人がその話を聞いて胡散臭げに呟く。
ひがみだろう。
自分達のような人間が手に入れることの出来ない物を偶然でも買うことのできた自分に対して。
『つーかさ、偽物じゃないの?』
なんとでも言えばいい。
その偽物すら希少価値が付いて、手に入らないのだから。
『高級車の場合、悲惨な事故車だったりするよね』
何かの曰くが在るんじゃないと脅してきた友人もいたが、すべて笑い飛ばした。
笑い飛ばさなければ・・・・良かった。
とぅるるるるるる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とぅるるるるるる・・・・・・・・・
電話は、変わらず青く光りながら鳴り響く。
だが、その受話器が取られることはなかった。
枯れ枝のようにやせ細った少女が、部屋の片隅で丸くなっている姿だけが、闇の中に浮かび上がる。
終わりを望んだ少女がどれほど望んでも潰えてなかった音が、まるで不意に途切れるが、ディスプレイの灯りは消えず、【着信】の表示が【通話中】に変わる。
一秒・・・二秒・・・・三秒とゆっくりと時間が刻まれ、息づかいのような音だけがスピーカーから漏れる。
さらに時間は進み、ふいに空気が笑う・・・・・・
|