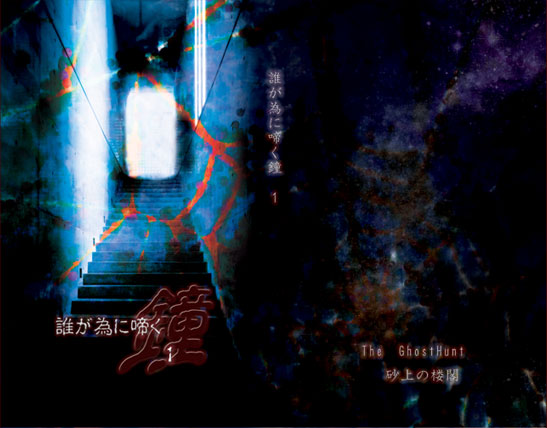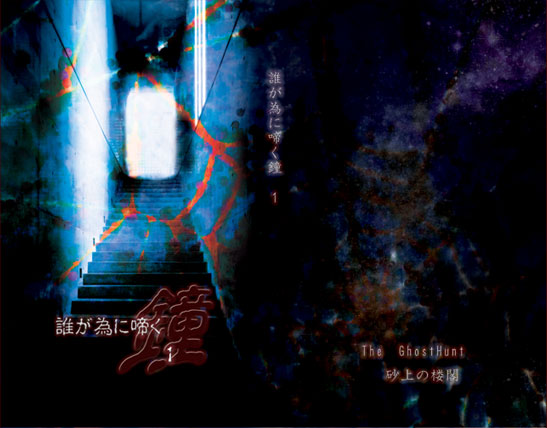序章
「エルフリーデ!!」
赤く立ち上る炎
鼻を突くタンパク質が焦げる臭い。
赤い炎に包まれた抱き合う二つの姿。
それを凝視しながら、壮年の男は叫ぶ。
「なぜだ・・・エルフリーデ!!」
聞く者の胸に突き刺さるような悲痛な叫び声が辺りに轟く。
「許さん・・・・私を裏切ることは許さん!!」
男は暗い炎を両目に宿しながら、赤々と燃える炎を見据える。
暗く澱んだ双眸に映りこむ赤い炎はまるで、血が双眸の中で輝いているように、怪しげな光を放つ。
「伯爵様!」
騒ぎを聞きつけた使用人達が、バケツを手に持ち火の衣を纏った二つの人影に次々と放つ。
水を掛けられ砂を掛けられ、それは瞬く間に勢いを無くし、その場には黒く焼かれた二人だけが残る。
生きているのか死んでいるのかそれさえも定かではない。ただ、地獄の業火のような炎にその身を焼かれても、二人は離れることを厭うかのように抱きしめ合っていた。
まだ白い煙を発するそれを、壮年の男は無造作に蹴り飛ばす。
「・・・・っぅ・・・・・・・・・・・・・」
まだ息があったのか、蹴り飛ばされた方はうめき声を微かに漏らすが、男は氷のように冷たい眼差しで、それをにらみ据えると、背後に控える老齢の男に命じる。
「森に捨ておけ。野良犬どもが食らいつくだろう」
男の無常な言葉に、老齢の男は顔色一つ変えることなく頷き返す。
「お前にふさわしい最後だ。
死してもやらん。エルフレーデは未来永劫私の妻だ。お前如きにはけしてやらん・・・・」
老齢の男はさらに背後に控える男達に、処分の始末を言いつけると、伯爵と呼んだ男の背後に控える。
「奇跡的に奥様はまだご存命でございますが、ドクター・ドナルドでは手に負えぬとのことです。すぐに高名なお医師を呼びにハワードを走らせました」
主同様に感情を伺わせない声で老齢の男は淡々と報告する。
伯爵の妻は苦悶のうめき声を漏らしていた。
美しかった白い肌は見るも無惨に焼けただれ、見事なプラチナブロンドの髪は焼け落ち今やかけらも美しさを保ってはいなかった。
そんな妻を伯爵は冷たい眼差しで見下ろす。
「お前はけして死なせたりせぬ。エルフレーデ。永遠にお前は私のそばにおるのだ」
瀕死の妻を心配し、なんとしても助けようとしているとは思えないほど、冷たい声音。眼差し。
肌が焼け爛れようとも、ただ一つ変わらなかった蒼い双眸を女は夫へと向ける。
何かを呟いたように唇を動かすが、それは声にならなかった。
だが、伯爵は妻が何を呟いたのか理解し、その双眸にさらに陰湿な光を宿らせる。
「あの男を捨て置くのは待て。回復させろ」
唐突に伯爵は指示を変える。
男を助け傷の手当てをしろと指示をだす。
けして死なさないように。
「処分はその後でよい。
エルフレーデ・・・お前は知るであろう。
己がいかなる大罪を犯したのか。
私は許さないよ・・・私を裏切る者を」
男は暗い笑みを漏らす。
その声を女は意識の片隅で聞いていたが、それ以上意識を保つことができず、暗い笑い声を聞きながら、闇の世界に落ちてゆく。
最後に呟いた言葉は神への祈り。
冒涜を犯した身であれど、祈らずには射られなかった。
そして、全て始まる前。
悲劇の幕が上がった瞬間。
憎しみの連鎖。
消えることのない憎悪。
狂った伯爵が悲劇の歯車を回す。
◆
小国がひしめき合い、大国が侵略し、敵対関係にあろうとも血縁関係がひしめくヨーロッパ大陸の一角。
森を切り開き、至る所に村を作り、街をお越し、税を取り立てる城を築いた人間達の魔手を拒むように、どこまでも続く黒い森に覆われた険しい山脈。
頂を夏でも白く染める山を望む黒い森は、時折何かの獣が濃い闇の奥に走り抜けるぐらいで、生き物の気配が感じられないほどひっそりとしている。
旅人も通り抜けないような、地の果てまで続くような暗い森。この土地に住まう物は野谷を駆け回る獣たちか、妖精達か。そう思わせるほどそこには人の気配が感じられなかった。
だが、黒い森を延々と歩いていくと不意に視界が開ける。
まるで、夢の世界に紛れ込んでしまったかのような錯覚に陥ったのは、太陽の日射しを金色に弾く煌めきが視界いっぱいに広がっただろうか。
険しい山脈に沿うように広がった黒い森の中で、ぽっかりとうがたれた平地。そこには風になびく小麦が重く頭を垂らし、黄金に輝く穂を風になびかせていた。
森同様に音という音はほとんど聞こえてこない。
ただ、さくり・・・さくり・・・実った小麦を刈り取る音だけが、唯一の音とかす。
人の気配など森の中にはなかったというのに、当たり前のようにその小麦畑の中には人がいた。だが、誰一人口を開かず、まるで言葉を忘れてしまったかのように・・・いや言葉という存在を知らないかのように、誰一人会話を交わすことなく黙々と刈り取っていた。
朝から晩まで。一年中変わらずまるで機械仕掛けのおもちゃのように彼らは同じ動きをし続けていたが、唐突にその手を止めて曲げていた腰を伸ばすと一様に顔を上げて何かに引き寄せられるかのように遠くへと視線を運ぶ。
変わらず言葉は発せられなかったが、ほぼ同時と言っていいほど皆が一様に眉間に皺を刻む。
低く・・・重々しい音が風に乗って流れてきたのを合図にしたかのように。
静かに鐘が鳴り響く。重々しい音が全てを飲み込むように。
空気を重く沈める音だ。
「・・・またか」
重々しい音を忌むかのように、誰かが呟く。
風に乗って聞こえてきた鐘の音は13回。それは、祝意をもたらす数ではない。誰かの首元に死神の鎌が振り下ろされた合図。
「今度は誰が死んだんだ?」
「さぁな。どうせ、ご城主がどこからか買い入れてきた奴隷だろう。わしらには関係ない」
「奴隷如きで弔いの鐘がなるわけがないだろう」
「なら、御身内か家臣の誰かの弔いだろ。いまさら珍しいことじゃないさ。
あの城のなかだけ奇妙な病が流行っているんだからな。まぁ城の中だけで流行っているならいいけどよ」
「めったなことを言うのはおよし、どこで誰が聞いているか判らないんだからね」
「旅人に聞かれてみろ、この村は城もろとも焼き捨てられんだぞ」
「ユゲルント村で奇病で死んだ人間がでたとかで、領主様に村ごと燃やされたって聞いたぞ」
人々は声を潜めてぼそぼそと言葉を交わす。
「なぁ、本当に奇病なのか? いくら城を閉ざしているからと言ってもよ、村では一人もでないのはおかしくないか?」
普通に考えるのならば、城の中で流行るよりも先に貧しい村人達の誰かが病にかかる。
それが、スタートだ。
だが、この村で・・・いや、城の中で流行っている病は違う。城の中でしか死者はでない。
それも流行病と言うには、間隔がどうもおかしい。
「ユゲルント村で病が流行ったときは、十日でバタバタ人が死んだって話だけどよ」
「なぁ、おかしな噂きかねーか?」
村人達は顔を見合わせるとごくりと唾を音を立てて飲み込む。
おかしな噂。
はっきりとした事は誰にも判らない。
ただ、妙な噂を聞いたことがある。
どこから、そんな噂が出始めたのか・・・それすら判らない。
だが、無視をするにはあまりにも問題のある噂。領主にそんな話を聞かれたら拷問の上一家皆殺しにされかねない。
厚い城壁の向こうで何が起きているのか、誰も知らない・・・
「噂が本当なら・・・・」
「んなことわからんよ。
城にいった人間はもう何年も戻ってこないか・・・」
「しっ、ミゲイル坊がいる。坊のトコの母親が先週城にあがっているんだ」
まだ幼い少年が不思議そうな顔で自分達を見ていることに気が付くと、誰もが一瞬にして口を閉ざす。
「お母さんがどうしたの?」
少年特有の高い声が重い空気を壊すように響く。
「いや、なんでもないよ。それよりミゲイル坊どこにいくんだい?」
「森にチコの実を採りに行くの。ムッターが採りにいけないから替わりにいっておいてあげるの」
「良い子だね。だけど、奥にはいっちゃいけないよ。危ないからね」
「はーい」
少年は満面の笑みを浮かべると、大人達に背を向けて黒い森の中へ走り出していく。
その背中を見送りながら、誰ともなく重々しいため息を吐き出す。
どこで、一体何が狂ってしまったのか誰も判らなず、誰も知ろうともしない。
ただ、ここ数年の間で一体何回聞いたかわからない音を今日も聞く。
この村ではけして珍しいことではなくなってしまった、慣れ親しんだ日常。
だが、それは明らかに異常だということを皆は知っていた。知っているが彼らに何かが出来るわけではない。
何も力をもたない無力な存在。
領主の掌の上で踊らされるように生かされている存在。
何かを視ても、何かを聞いても、何かを知っても、理解してはいけない。
目を閉ざし、耳を塞ぎ、口を塞がなければ生きていけないのだ。この世界で生きる限り、抗う術など彼らにはない。
だからこそ不安が残る。
自分達の世界を壊す何かが、直ぐ近くで起きているのではないかと。
深い森と厚い石壁の奥で何かが動いていると・・・
まるで、城内だけが別の世界のように、奇病が流行っている・・・・・・・それが、どんな奇病なのか誰も知らない。
ただ、時折、弔いの鐘の音色が風に凪がれて聞こえてくることが死者を出たことを村人達に知らせるだけだ。
その屍体は村人達の目に付くこともない。
葬儀を表立って営まれることもなく、誰が死んだのかもけして伝えられない。
村の中から呼ばれた者なのか、外から呼ばれた者なのか。それさえも判明しない。
そもそもなぜ、定期的に人を城に呼ぶのか。けして広大な城ではない。ほんの数年前までは領主すら滅多に訪れないような忘れられた城だった。
人手が足りなくなるような状況ではなかったはずだ。維持をするだけの最小限の使用人で十分だった。少なくとも、村人の記憶にある限り。
だが、気が付けばいつのまにか領主はあの城に留まり続け、時を同じくして鐘が頻繁に鳴り始めるようになり、人手が足りないからと、村の人間が男女問わず城に雇われる事ようになった。
時折奴隷を何処からか買ってくる事もある。
しかしけして、近隣の土地からの人間が使用人として雇われる事はない。何かを恐れ避けるように、村人を城に召し抱えるか、遠方から奴隷を買ってくる。
村長が一度だけ、隣村の若者を斡旋しようとしたことがあったが、酷い叱りを受けることになり、それ以降村の者が迂闊に外部の者に、領主が使用人を募集していることを明かすことはなくなった。
なぜ、そこまで外部の者を怖れるのか、いったい何のために使用人を幾度も増やすのか、村人達には判らないが、触れてはいけない話題だと言うことだけは悟らないわけにはいかない。
話題にしてはならず、質問を問いかけてもならない。
答えをしる奴隷と顔を合わせることもなければ、身内たる村の者とも連絡をとることはできず、ただ静に降り積もる雪の如く、不安を募らせていくことしかできない。
閉ざされた世界。
誰も外にでる事は出来ず、外のものは誰も中に入ることが出来ない。
物理的に行き来はあろうとも、精神的に深い交流を持つ事はけしてなかった。
誰がこの世を去ったのか判らないが、村人達は鐘が鳴り終わる前に、帽子を取りそっと目を伏せると胸の前で十字を切る。
迷うことなく神の御許にたどりつけるように。
天へと続く道が光りに照らされているように。
哀しい慟哭のように、今日も鳴り響く。
まるで、神に慈悲を請うかのように
その鐘がなぜなるのか、誰も知らない・・・・・・・
それは、どれほど月日が流れようとも変わらない。
城の主が何代にわたろうとも・・・・・・・・
世界がどれほど移ろい行こうとも、声なき声のように鐘は鳴り響く。
重い音の連なりと化して
「誰か・・・・御願い、あの人を救って 」
いつの時代か、誰のものかわからない、掠れた力弱い救いを求める声が鐘の音にかき消される。
|