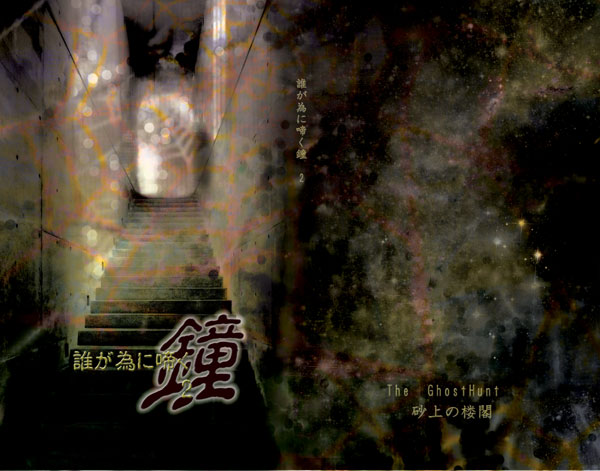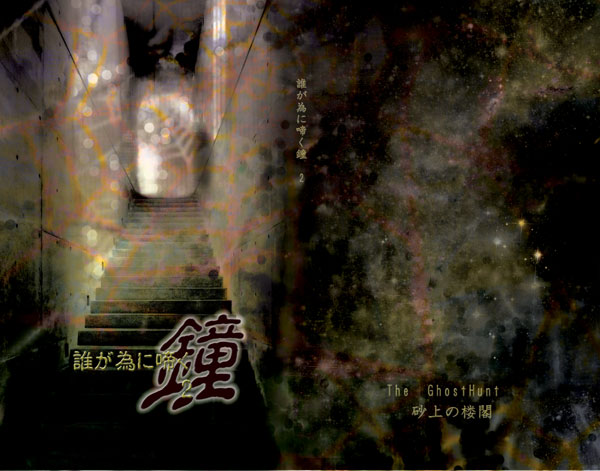五章より抜粋
犬の遠吠えが耳につく。
それとも狼の遠吠えだろうか?
細く・・・長く・・・・・・かすかに聞こえる。
風に乗りどこからか聞こえてくる・・・・・・・・・
ヒタヒタヒタ・・・・と
なんの音だろう。
獣の鳴き声でもなく、風が吹き抜ける音でもない。
何かがこすれるような音・・・・
眠気が強く意識がはっきりとしない。
自分が起きているのか眠っているのか、現と夢を行き来しているような曖昧な感覚。
形成した端から、とろとろと溶けて行くようで、意識を一つの事に保つことができなかった。
ぺたり・・・ぺたり・・・
まるで、床の上を素足で移動していくような音。
誰かが廊下を移動している音が聞こえてくるのだろうか。
遠くから少しずつゆっくりと音が近づいてくる。
少し進んでふいに止まり、音が消えたかと思うとまた、ゆっくりと近づいてくる。
微かに聞こえていた音が、だんだんとはっきりと。
ぺたり、ぺたり、ぺたり。
また、止まる。
まるで、何かを確認しているように。
確認?
麻衣はそこで漸く何かがおかしい事に気がつく。
何かがではない。
何もかもだ。
ここは普通の造りの家屋ではない。
厚さ数十センチはある石の壁でできた城。
部屋には窓という窓がないため密室に近く、その分厚い壁によって廊下の音が室内に聞こえてくることはまずありえない。
よほど大きな物音でもない限り、木で出来たドアをノックする落としか聞こえてこないにもかかわらず、なぜ足音が聞こえてくるのだろうか。
そのうえ冷たい石の上を素足で移動する人がこの城の中にいるのだろうか。
背中を冷たい汗が流れる。
考えれば考えるほど、おかしな状況にいきつく。
少しずつ近づいてくる音。
使用人が廊下の明かりのチェックをしているのだろうか。そう考えれば、少し進んで立ち止まるのは判るのだが、素足で彼女たちが歩くはずがない。
なにより、麻衣が異常に感じるのはなぜ、足音が聞こえるかだ。
今まで誰が外を通っても聞こえなかったというのに。
その音は徐々に近づいてくる。
眼を開けて四方へ視線を巡らせるが、明かりのない部屋では部屋の輪郭さえ判らず、完全な闇に包まれている。
それでも、麻衣は眼を凝らして四方の壁へと視線を向ける。何も見えないがそれでもそこには、綾子が用意した護符がしっかりと貼られているはずだ。例え、生きた人ではなくてもそう簡単に室内には入って来れないはずだ。
今までの経験で考えるなら。
だが、ここは日本ではなく神道の意識などかけらもない遠い異国の地。
果たしてあの護符がどのていど西洋の霊に効くのだろうか。
現代の日本人は宗教概念が曖昧なせいか、それとも、まさに太古の時代から八百万の神々を信仰してきた風習があるからなのか、キリスト教の祈りだろうと、神道だろうと仏教だろうと、霊に対し効果は出ていた。
はたしてキリスト教の概念を根強く持っている欧米諸国ではどうなのだろうか。
キリスト教信徒にとって神の教え以外無用の長物ならば、綾子の用意した護符は、見たことのない象形文字のようなものが連なって白い紙にかかれ、壁に無造作に貼り付けられているだけとしか映らず、何の役割も果たさないかもしれない。
だが、一般的な日本人もそこに書かれている字は読めないのだから、字の読解には関係なく効果があるのだろうか。
ぺたり・・・ぺたり・・・ぺたり
部屋の扉の前で止まったのが判る。
今まで同様に数秒だけで移動するのだろうか。
緊張で身体が強ばり、じっとりと嫌な汗が手のひらに浮かぶ。
それは、なかなかその場から移動しようとしなかった。
息を潜めてじっと扉を見ているような気がするのだが、本当に・・・廊下の向こうに人はいるのだろうか。
じっと、まるで中の気配を伺うように立ちつくしているようにも、ただ単に神経過敏になった自分の思いこみのようにも感じてくる。
これは夢の中の出来事だったのだろうか。
今は自分はちゃんと起きている?
それとも夢?
そもそも、自分はいつ眠りについてしまったんだろうか。部屋に戻った記憶も、ベッドに潜り込んだ記憶もない。
なぜ、ベッドに横になっているのだろう。
ドキンと。心臓が強く鼓動を打つ。
心臓が五月蠅いほど早鐘を打ち存在を主張し、身体がキンっと冷えてゆく。
寒い。
暖炉もすっかりと消えてしまい、部屋を暖める役割を果たしてないのだから冷えていくのは当然だが、暖かな毛布にくるまっているはずだというのに寒い。
歯の根が噛み合わず、ガチガチと音を立てる。
寝汗で身体が冷えたといえるようなレベルではない。
全てを凍て付かせるような冷たい空気が、足下からジワジワと忍び込んでくる。
いったい何が近づいてきているのか。確認するように眼をどんなに凝らしても、見える物など何一つ無い。
聞こえてくる音も、銃眼を通り抜ける風の音だけだ。その音すら今は人の悲鳴のように聞こえてくる。
あの、扉の向こうに何かがいる。
何か・・・じゃない。
あの、白いドレスを着た女だ。
最後に覚えている事は、白いドレスを着た女のこと。
フロから戻る途中に遭遇した、この城を徘徊すると言われている女の霊。
扉越しに彼女が立ちつくして、じっと自分を見ているような気がした。
いや、気がするだけではない。
彼女は視ている。
扉越しに・・・・分厚い壁など目の前にはないかのように、その場に立ちつくして自分を見ている。
ややうつむきがちに首をさげ、顔を覆い隠す髪の隙間から、強い視線をなげうってくる。
むろん想像でしかない。
麻衣には厚い壁の向う側の様子など何一つ判らない。
だが、強い視線を感じる。
眼をそらすことを許さないように。
彼女は両腕をあげて力一杯扉を押す。
普通なら弾かれるはずだ。
綾子の結界が貼られているのだから。
だが、まるでそんなものは自分には関係ないと言わんばかりに、女が扉を押すと微かな軋み音一つ立てず扉が開く。
麻衣はその様子を瞬き一つせず凝視し続ける。
なぜ、明かり一つない部屋で、彼女の行動がはっきり見えるのだろうかとか、そんな事ももうすでに疑問に浮かぶ余地はなかった。
ただ、全てを凍て付かせるような冷たい空気にさらされ凍えた身体を、何一つ自分の自由に動かすことができず、ただ同じ姿勢で少しずつ近づいてくる彼女を見ていることしか出来ない。
Halten・・・・
カサカサに乾涸らびた唇から、低いうめき声のような音が漏れる。
声を聞いただけでは男なのか、女なのか判らない。
彼女はゆっくりと近づいてくる。
怖いと。なぜか思わなかった。
吐き出す呼気は凍て付いた空気に冷やされ白く棚引き、身体はあいかわらず自分の意思では指一本動かせられない。
にもかかわらず、なぜか怖いと思うことはなかった。
おそらく、彼女は自分に危害を加える気はないのだ。だからこそ、恐怖を感じない。
だが、だからといって危険がないという事にはならないことは判っている。本人に危害を加える意思がなかったとしても、結果的に命に関わるような状況になることもあるのだ。
生者ではなくなり、己の妄執に取り憑かれた存在と化しているさまよえる者達は、生者としての概念を持たない。
故に害意はなくとも危険がないとは限らない。
だが、だからといって今の麻衣にはどうすることも出来ない。
九字を切ろうにも指一本動かすこともできず、助けを呼びたくても声が出せないのだから。
金縛り状態だった。
心の声を聞いてナルが来てくれる。など今時どこの少女小説ですか!?と言いたくなるような展開など当然望めない。
なら、腹をくくるしかない。
彼女がなぜ、自分の元に来るのか。
何を言いたいのか。
あの時も彼女は何かを言っていた。
だが、聞き取れる前に消えてしまったのだ。
今度こそ、何を訴えたいのか聞き逃さないように。
強い意志を込めて、自分を見下ろす彼女を見上げる。
その意志を感じ取ったのか、はたまたただの偶然か。彼女は乾涸らびた唇をゆっくりと動かす。
Halten Sie zwei Personen an.
死んだら意思は言語を関係なく共通して理解できるのかと思ったのだが、そうは簡単にはいかないようだ。
何を言っているのか全くと言っていいほど判らなかった。
英語ではないことだけは判る。
城のある場所を考えればドイツ語の可能性は高いが、断定は出来ない。古い時代ドイツは小国の領土に分断され、それによって使用されていた言語も違うだろう。
判ることは、自分が知っている言語ではないという事だけ。
意味のある言葉なのか、それともないのか。それすら当然判らない。
ただ、それでも彼女が何を言っているのかを必死で覚える。意味は判らずとも音のニュアンスを覚えておけば、ナルなら判るかもしれない。
麻衣の英語の問い掛けに判って返答しているのか、それともただ己の欲求を訴えているのか判らない。
ただ、彼女は繰り返す。
嗄れた声で。
幾度も幾度も。
おそらく、地下でも聞いた言葉を。
Halten Sie zwei Personen an.. と
|