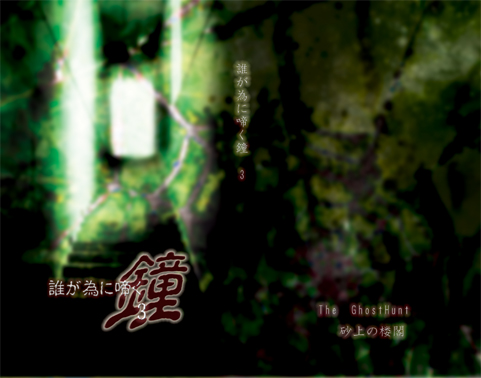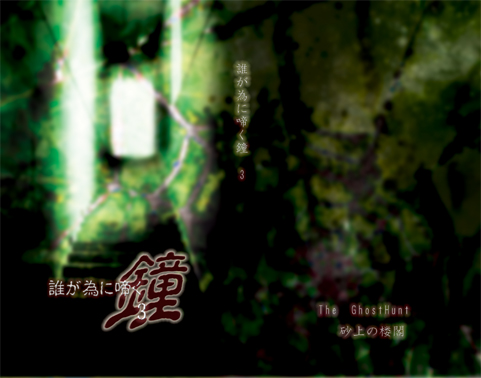幕間より
「おかあさまはどうして毎日泣いていらっしゃるのかしら?」
鏡の前にちょこんと腰掛けた少女は鏡越しに乳母を見つめながら、問いかける。
その問いに乳母は返事が咄嗟に出来ず、困ったような微笑を浮かべながら、少女の艶やかな黒髪を梳いてゆく。
「わたくしが、おとうさまに愛されないからおかあさまはないていらっしゃるの?」
「そのようなことはございませんよ。お父上さまはお嬢様のことをことのほか大切になされております」
咄嗟に少女の言葉を否定するが、少女は乳母の言葉を鵜呑みにすることはできなかった。
自分が愛されているかどうか、どんなに幼くとも判る。理屈ではなく本能で判ってしまうものだ。
まして、年よりも聡明で感受性の強い子供なら否応なく気がついてしまう。
自分が、父に愛されていない。ということを。
その事を乳母も判っている。
産まれたときから我が子のように面倒を見てきたのだから・・・いや、実の子よりも長く共にいるのだから。
自分が仕える主にとっても、乳母である彼女は実の母よりも共にいる時間が長かった。だが、それでもけして親子のような関係にはならない・・・いや、なれない。
幼い少女は主で、自分は彼女に仕える立場の人間である以上。
「ねぇ、ばあや。どうすれば、おとうさまに愛していただけるのかしら?
この髪がおかあさまのように綺麗な金髪だったら愛してくださるのかしら。
この瞳がおかあさまのようにエメラルドのような色だったら愛してくださるのかしら。
この肌がおかあさまのように白かったら愛してくださるのかしら。
ねぇ、どうすれば愛してくださると思う?」
幼い・・・まだ年端もいかない少女の問いに、乳母は返答に詰まる。
聡明な少女に嘘は通じない。
その場限りの慰めの言葉も、誤魔化しもすべて見破ってしまう。
幼い故に敏感だった。
愛して欲しい・・・心から強く望んでいるだけに、少女は飢えていた。
「お嬢様がお母様のように、美しくご聡明で素敵なご令嬢におなりあそばせば、お父様もたいそうお喜びになられるかと思います」
そう言うのが精一杯だった。
彼女の父が娘を顧みることはおそらく一生無い。
乳母はそれを確信していたが、だからといって事実を幼い・・・まだ、何も知らない娘に伝えることなど出来ない。
いずれ・・・おそらく、そう遠くないうちに少女はなぜ自分が父に愛されないのか判ってしまうだろう。
誰も告げずとも、聡明さ故に悟ってしまう日がそう遠くないうちにくる。
たとえ、屋敷中の人間が口を閉ざし、彼女の疑問に答えを告げずとも。己の中から答えを見つけてしまう。
だから、その日が出来るだけ遅いことを祈ることしか出来なかった。
乳母はそれ以上少女をまっすぐ見ることが出来ず、目を伏せながら黒く艶やかな輝きを放つ髪をとかし続けていたため、少女のブルーの双眸がまっすぐ乳母を見続けていたことに気が付かない。
その瞳が酷く冷め、年に不似合いだと言うことに。
愛して欲しいの。
私を見て欲しいの。
ここにいることを判って欲しい。
触れて欲しい。
認めて欲しい。
わたしを。
どうすれば愛してくれるのかしら?
髪を母と同じ色にすればいいのかしら?
目の色を母と同じにすればいいのかしら?
肌の色を母と同じにすればいいのかしら?
立ち居振る舞いも、話し方も、視線の配り方も、服の好みから、髪型、何もかも同じにすれば愛してくれる?
ねぇ・・・おとうさま
どうすれば、私を見てくれるの・・・・?
なぜ、わたしをみてくれないの?
そんなに私がきらい?
この黒髪も
このくすんだブルーの瞳も
象牙色の肌も
捨てろと言うのなら惜しげもなくすてるわ。
だから、私を見て・・・・
私を愛して。
私以外を見ないで・・・
おとうさま、おとうさま、おとうさま、わたしを見て私を愛して私に気が付いて愛して御願いお父様愛して御願い御願いなんでも言うことを聞くからお父様の望みの通りの娘になるからどうか私を愛して。
「愛して貰いたいのね」
暗い想いの中に甘い蜜のような声がゆっくりと広がってゆく。
「・・・・ええ・・・あいしてほしいの 」
幼い子供が話すような舌っ足らずの言葉に、声の主は微笑を零す。
「愛して貰えるように手助けをしてさしあげますわ」
「ほんとう・・・・?」
「嘘は申しませんわ。
ゆっくりと目を閉じてくださいな。
貴方の中に貴方が愛して止まない方を想い浮かべて。そして、その方が愛して止まない方も・・・ああ、苦しまないで。
その方は貴方でもあるんですのよ」
「わたし?」
「そうですわ。
ご自分の中にしっかりと思い浮かべて。
その方は貴方自身でもありますのよ」
「ちがうわ。
だって、おとうさまが愛していらっしゃるのはわたしではなくて、おかあさまですもの。わたしではないわ」
「否定なさらないで。
否定してしまうと自分をも否定してしまうことになりますのよ。
受け入れて・・・その方はあなた。
貴方が愛してる方が愛してる人は貴方なんですもの・・・受け入れて・・・・そう、呼吸を楽にして。
ゆっくりと貴方の中で解けて、貴方の全てが染まる時、貴方は愛した方の愛を手に入れることができますわ」
「ほんとう?」
「ええ・・・ですから、抵抗なさらず受け入れて」
瞼の上に甘い香りを放つタオルを乗せられる。
何の香りなのだろうか。
一呼吸する事に身体から力が抜けてゆき、瞼が次第に重くなってゆく。
「さぁ・・・心をゆだねて 」
女の声が酷くゆっくりと・・・掠れて聞こえる。
「・・・大丈夫ですわ。何も心配することなどありませんのよ。きっと愛してくださいますもの。あなたが になれれば」
身体が鉛のように重くなり、瞼は膠で貼り付けられたかのように自分の意思では開くことも出来ず、声も出すこともできず、指一本動かすことも出来ない。対抗しようともその力にあらがえない。
だが、暗い闇の中で意識は消えることなく存在し、女の言葉を否定し続ける。
そんなことで愛しい人が手に入るわけがないと。
あの人の愛を勝ち取るためなら、私は何だってするわ。
少女の唇が毒婦のように一瞬歪むが、人目に付くことなくそれは直ぐにほどけて消える。
たとえ、何を植え込まれようとも・・・想いは変わらない。
|