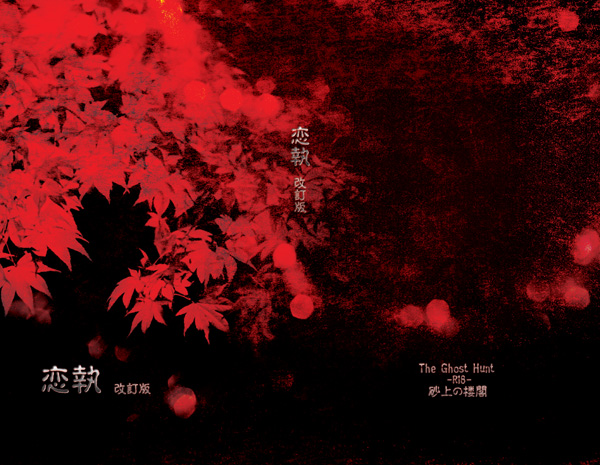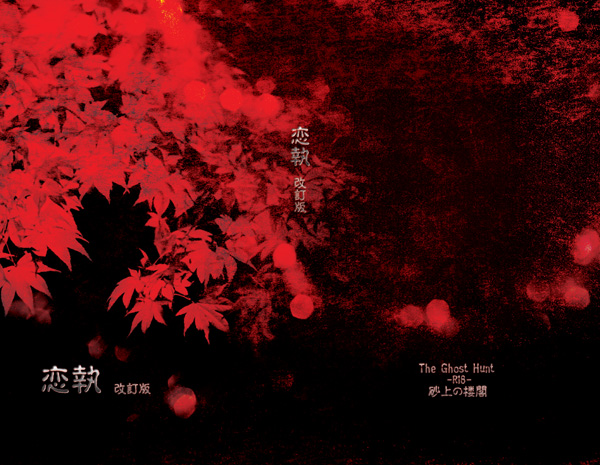序章
きっかけはなんだろうか。
少年達の軽い気持ちから始まったゲームにしか過ぎないはずだった。
それが、後に災いを産むことになるなど、この時誰一人想像しなかっただろう。いや、出来るわけがない。
少年達にとって、きっかけはあまりにも日常茶飯事過ぎた。
いつもとなんら代わり映えのしない、会話の流れからたどり着いたのだから。
誰一人それが、災いを招くことになるなど・・・災いを招くほど執着する結果になるなど、誰にも想像つかなかった。
本人でさえ
「柳瀬君! 柳瀬君<」
校門から飛び出して来た少女は脇目もふらずに、一人の少年に向かって駆け出す。それほど長い距離を走ったわけではないが、息は切れ冷たい風に当たった頬が赤く紅潮していた。
名前を呼ばれて足を止めた少年は、記憶にない少女を見て軽く眉を潜める。
最高学年である自分を「君」で呼ぶのだから無条件に同級なのだろうが、三学年は四一五人いるため、同級か倶楽部でも同じにならない限り一目見て判るわけがない。
もしくは、よほどの有名人か・・・
自分は顔は広い方だとは思うがそれでも目の前の少女が誰か判らなかった。
ややぽっちゃりとした体形、黒く艶やかな髪を左右に結い、スカート丈は今時珍しく膝下。ソックスも靴も学校規定のもの。絵に描いたような生真面目すぎる・・・今時普通でももう少し砕けていると思うが生徒・・・・すぎて、印象がまったくなかった。
一瞬でそこまで観察すると、柳瀬はあからさまにため息をつく。
まじめ一辺倒な人間が声を掛けて来るとなると、用件は簡単に検討がついた。
掃除をさぼって帰宅しようとする自分を諫めに来た・・・とするならば、同じクラスの人間しか考えられないため該当外。見知らぬ女生徒が帰り際に声を掛けたとなると理由は一つしか思い当たらない。
その予想は自分一人だけではなく、周りにいた友人も同様なのだろう。人の悪い笑みを浮かべて少し距離を置いて見守っている・・・ふりをしながら冷やかしている。
「で? なに?」
気だるそうな声に宿る感情など少女は察することなく、息を切らしたまま震えて上ずっている声を絞り出す。
「柳瀬君!」
「だから、さっきからなに? 俺、用事があんだけどさ。用があるならさっさといってくんない?」
相手をする気など欠片もないという匂いを漂わせながら言っても、すでに自分のことで一杯一杯の少女には察することなど出来ず、興奮状態にあるのか目を潤ませて柳瀬を見上げた。
勘弁してくれ・・・・
柳瀬は微かに唇を動かして声を漏らすが、少女にはその呟きは聞こえず、顔を真っ赤にして叫ぶ。
「・・・入学した時からずっと、好きでしたっっ!」
柳瀬と呼ばれた少年は、自分を見上げてくる少女を一瞥すると、気がなさそうな態度を隠そうともせずこめかみを掻く。
少女は真っ赤な顔で俯いているため、そんな柳瀬の態度には気がつかない。ただ地面を凝視しながら、彼の返事を待っているようだ。
「で?」
「・・・・・・・・・・え?」
柳瀬の思いにもよらない反応に少女は少しばかり戸惑った表情を浮かべる。
「いや、だからさ。俺を好きだっていうのは聞いたけどだからなに?」
「・・・・・・・・なに・・・・って 」
柳瀬は大きなため息をつくと、後頭部を無造作に掻く。
「だから、何が言いたいわけ?
好きだって叫んでおしまいならさ、コウイヲクレテドウモアリガトウ。な感じなんだけど?
他に言うことがないならもういい? 俺、用事があるんだよね」
柳瀬の言葉に少し離れたところにいた友人達は、鬼だ、悪魔だ。極悪だ。等と好き勝手なことを言っているが、柳瀬からしてみればいちいち相手をしていられなかった。
卒業を数ヶ月後に控えた三学年。もう今年も残り僅かとなったせいか、こんな感じで見知らぬ女生徒から告白されることは少なくなかった。
やっかみの十や二十を買いかねないほど、告白ラッシュが柳瀬に押しかけていたが、本人からしてみればいい迷惑であったため、こんな面倒な事は早く終わらせてしまいたかった。
「・・・・・・・・・・好きだから・・・・」
そんなあからさまな柳瀬の態度に、最初の勢いはすっかりとナリを顰め、尻すぼみに声がだんだんと小さくなっていく。
「悪いけどさ、好意の押しつけやめてくんない?
好きだからなに? 俺に付きあえって? 冗談でしょう?
どんな噂聞いているのかしらねーけどさ、見も知らない女と付き合うわけないだろう」
「みもしらないなんて・・・」
「あんたは俺を知っているみたいだけど、あんたが誰か俺知らないしさ。俺等の学年四百人以上いるんだぜ? 把握するわけねーだろう。自分が知っているからって相手も自分のこと知っているなんて、自惚れたこと考えてないよな?
それともなに? 俺が疎いだけであんたって実はけっこう有名なわけ?」
少女は瞬間的に顔をかっと赤く染める。
「あんた、夢見がちなってやつ?
自分の視線に気が付いてくれていて、実は両思いだったなんて寒い夢見てないよね?」
柳瀬の言う言葉は図星ですと言わんばかりに、重みに耐えられなくなるかのように下を向いていく。
「俺の何を知っているのかしらねーし、興味もねーけれど、彼氏欲しいだけなら他あたってくれる?」
柳瀬はそれだけを言い残すと、それ以上は少女の言葉を聞こうとすることなく身を翻すと、さっさとその場から離れていく。
少女はまだ何かを言い足そうに、慌てて顔を上げて柳瀬を呼び止めるが、柳瀬は今度は足を止めることなく校門へと向かっていく。
「相変わらずもてるねぇ。羨ましい限りだ。
少しぐらいなら付き合ってやってもいいんじゃねーの?」
少し離れて様子を伺っていた悪友の一人が、肩に腕を回しながら冷やかしてくる。
「冗談じゃねーつーの。誰があんな女と付き合えるかって言うんだ」
柳瀬は不機嫌もあらわに友人達のからかいを跳ね除けるが、友人達は柳瀬のそんな様子に構うことはなかった。
「そんな言い方しちゃ可哀想だぜ。
あの子にとっちゃ高校時代の素敵な思い出になるだろうしさ。ボランティア、ボランティア。淡い青春を謳歌ってヤツ? させてやれよ。
どう好意的に見ても、男と付き合ったことなさそうだしな。高校卒業する前に彼氏欲しいっていう気持ちはよーく判るんだよなぁ。
どうせ、お前は遊びなれているんだから、たまには毛色の違うのと付き合うのも面白いんじゃねーの? 毎度毎度、遊び慣れている女じゃ食傷気味にならね? 後腐れなくていいかもしれねーけどよ」
「うるせーな。なら、お前が付き合ってやれば?
俺はあいにくとボランティア精神に溢れてないんでね。そう言うのは博愛主義に任せるさ」
柳瀬と呼ばれた少年は辟易とした態度を隠そうともせず、友人達を一瞥するが、友人達は気にした様子もなく肩をすくめる。
「冗談。俺はオネーサマタイプが好みなの。悪いけどガキには興味なし」
自分はオトナだと言わんばかりの発言に、お前の方がガキだよとヤジが入る。
「俺は、こうぽちゃっとしたカワイコチャンがいいかな。ぷにっとした感じの。ああいうのはぽっちゃりを通り過ぎて肥えすぎだ」
「俺はこう、筋肉がきゅっと引き締まっているスポーツ少女が好みだな。弾力のある太股触るのが気持ちいんだよ」
好き勝手言い合う友人達の意見など軽く聞き流しながら、柳瀬は嫌悪感を隠す様子もなく顔をしかめてはっきりと言い切る。
「たまには毛色が違うのもいいけど、あの手合いだけは勘弁してくれ。冗談じゃすまなくなりそうでこえーよ。
一度でも親切心みせたら、スッポン並に食い付いて離れなさそうじゃないか」
「言えてる言えてる。ああいう真面目一直線の子は冗談も何もわからねーで、本気でとっちまうわな。
女に不自由していても絶対に相手にしたくないタイプだ。他の女と話しているだけでうだうだ言ってきそう」
「イベント事に手作り品ってか?」
「めちゃ惚れている女の子から手作りは嬉しいけれど、じゃなかったら勘弁してほしいよな! 女ってなんでもかんでも手作りに拘るけどさ、あれってけっこう貰う方って重いんだよなぁ」
想像するだけでも嫌なのか、柳瀬は渋面を作って友人達を残していくかのようにさっさと歩き出すが、その後を追うように友人達も歩き出す。
「そーいや、お前珍しく今付き合っている子いないよな?」
とっかえひっかえ選り取りみどりといわんばかりに、一週間と間をおかず常に誰かしらと付き合っているはずの柳瀬が、驚いたことにここしばらく付き合っている女の話を聞いていなかった。
「なに、お前身辺整理でもしてんのかよ」
まるで結婚前の男が身辺整理でもするかのように、今まで付き合っていたガールフレンド達を整理し始め、今ではすっかりと身軽になってしまっているというのだから、驚きを隠せない。
だが、友人達の疑問は柳瀬の言葉で消える。
「狙っているのならいるよ」
「誰だよ」
今度はよほどの大物狙いなのか? 皆の頭の中に候補の顔がいくつか浮かぶが、柳瀬が告げた名は思いにもよらない名前だった。
「谷山麻衣」
「なに、お前おこちゃまに趣旨がえ?」
柳瀬の口から出た名前が意外だったのか、友人達は本気で驚く。
知らない人間の名ではなかった。
今まで柳瀬が見向きもしなかったタイプ・・・・同級生の一人の名。
目立つ存在ではないが、家庭環境故に何となく同級生達は彼女の存在を知ってはいたが、柳瀬が特別好意を向けるような対象ではなかった と、記憶している。
「そりゃ、確かに可愛いとは思うけど、どう見たっておこちゃまだぜ?
いきなり毛色違いすぎない?
だいたいさ、先のコと同じで谷山だって冗談で男と付き合うようなタイプには見えないけどな。そういうの嫌だって今言ったばっかりじゃねーか」
「俺、谷山はマジだよ」
「は!?」
それこそ思いにもよらない言葉に、友人達は目をまん丸にする。
今まで女に本気になるのはバカバカしいと公言してはばからなかった人間が、本気になったというのだから、驚かないわけがない。
「だから、女と縁切ったんだろうが」
確かに、柳瀬の身辺整理はその本気具合を伺わせる物があるが、だからといってそう直ぐには信じられないでいた。
「マジなの? お前の趣味って相変わらず広いんだか、節操なしなんだかわかんねーよな。
俺はもっとグラマラスな女がいいなぁ。谷山じゃ細すぎだって。ぎすぎすした感じはねーけど、胸とか腰かこうもっとこうだなぁ・・・・・・」
といって少年は両腕で輪郭を描くが、一体どこにそんなハリウッド女優みたいなボディーラインを持った女子高生がいるというのだろうか。
呆れた目で柳瀬は少年を見つつも、ニヤリと口角を歪める。
「良く見てみろって。確かにグラマーって体形じゃないけど、結構そそられる体形していると思うぞ。特に、今年に入ってから体つきが妙に女っぽくなっているね。
あれはたぶん、一皮剥けると化けるってタイプだね」
「そーか? 俺は相変わらず折れそうなほど細い身体にしか見えねーけどなぁ。こう、もっと肉感的なほうがいいと思うけど。
アレじゃ、抱き心地悪そうだ」
「見ていなって。近いうちに必ず落として見せるからよ。その後で後悔したって遅いからな」
「なに? お前マジで企んでいるわけ?
今どき光源氏計画なんてはやらねーつーの。だいたいそう言いながら相手にしていたのは、皆色々教えてくれるおねーさまタイプばっかだったじゃねーか」
「うるせーな。それは社会勉強。育てるには自分が知らなきゃできねーだろう」
「確かにそうだけどよ。それにしても計画性あるのかないのかわからんやつだな」
「うるせーな。だいたい、男のロマンだろ? 何も知らない純真無垢な女に一から教え込んで、自分好みにしたいっつーのはよ」
「俺はそんな面倒なロマンは趣味じゃないな」
「俺も。どうせなら、おねーさまに手取り足取り教えて貰いてーよ」
「面白くないやつらだな」
「でもさ、俺は幾らお前でも無理だと思うけど。
谷山っておこちゃまちっくだけど、かわいい部類には入るからな。何人かが告白したりしているみたいだけど、全滅だって話だし。
バイトが忙しいって言う理由だけど、お前が言う今年に入ってから女らしい身体になったて言うなら、彼氏でもいるのかもな。
すでに、手取り足取り色々教えてもらってんじゃねーの? どっかの誰かに」
「んなわけねーって。どうみたって、谷山はおこちゃまだぞ。下手したらキスすら知らねーかもしれねーじゃん。
それにバイトと学校の毎日で、どうやって彼氏つくれんの? 校内で作ったら、誰だって噂になるだろうし、その手の噂谷山にはないじゃねーか」
そんな一人の言葉にその場はにわかに沸き立つ。
谷山が落ちるか落ちないか。
そんな彼らを尻目に柳瀬は自信ありげに笑みを浮かべながら言い放つ。
「絶対に、俺のもんにしてやるさ」
「なら賭けないか? お前が谷山を落とせるかどうか」
「俺、ムリに二千!」
「俺もあっけなく振られるに、三千!」
その場にいた五人は皆柳瀬が振られる方にお金をかけていくが、柳瀬は自信ありげな笑みを崩すことはなかった。
自分が振られるわけがない。
その根拠はただの盲目的な思いこみにしかすぎず、裏付ける理由など何一つない。だが絶対の自信があるが故に、振られることなど柳瀬には想像できなかった。
「おっけい、なら俺の一人勝ち決定だな」
「今度ばかりは、お前の初黒星だな。経済面理由に男つくらねーなら無理だろう」
自信満々の柳瀬を冷やかすが、柳瀬は満面の笑みを崩さない。
「この俺が本気になっているんだぜ? 落とせないわけないだろう」
傲慢としかとれない言葉だが、少年達は誰もその言葉自体を否定せず、言葉の持つ意味を考えることもせず、無責任なまでに好き勝手に口々に言い放つ。
「手加減してやれよ。谷山はおこちゃまなんだからさ」
「俺やっぱり、変えようかなぁ」
「今更変更はなしだぜ」
柳瀬は確かに女に振られたことはない。
言い寄ってくる女は山のようにおり、柳瀬の方に選択権があった。
その柳瀬が自ら迫るのだから、落ちない女はいないだろう。
このかけはおそらく柳瀬が勝つ。
だが、それに賭けては面白くない。
だから、外れる方を狙う。
それがいつものパターン。
「俺の勝ち。だな」
誰もが疑わなかった。
その言葉通りになると思いこんで。
|