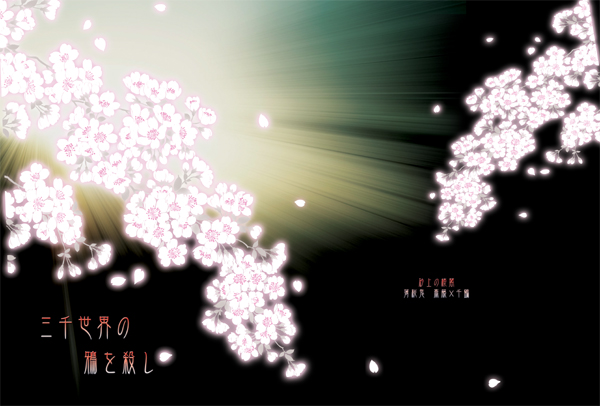序章&一章一部抜粋
瞼を閉じれば今も鮮やかに思い出すのは、ダンダラ模様が織り込まれた浅葱の衣。
女はどこまでも澄んだ青い空を見上げ、幾年月経とうとも脳裏に焼き付いて消えることのない、色鮮やかな衣を思い出す。
良くない噂は色々と耳にしていた。
野蛮とも殺人狂とも。
確かにいつも血の臭いを身に纏っていたかもしれない。
実際に血を見たわけではない。ただ、どことなくそんな雰囲気を常に感じてはいた。
だが、自分を買う男は噂とは違い乱暴な事は一切しない客で、夜の湖の水面の如く静かな双眸をした男だった。
噂は当てにならない。彼を見て女はいつもそう思っていた。
ただ、静かに酒を呑み、女を抱く。
そこに何か情めいた物が育まれることは無かった。
男は己のことを話す事は一度もなければ、女郎に睦言を呟く事もなく、けして、朝を共に迎えてはくれない客だった。
時々、ふらりと訪れて一時肌を重ねるだけの客。
そう、大勢いた客の一人に過ぎない。
甘く優しい一時を過ごす事もなく、男女の賭け事めいた艶めいたやりとりもなく、その付き合いは酷く淡泊なものだっただろう。
大得意様というほど頻繁に来ていたわけでもない。
いや、確かに初めは足繁くと言うわけではないが、定期的に足を運んでくれていた時期もあった。だが、気がつくと足の訪れはまばらになり、ふつりと途絶えてしまった。
そういう客が珍しいわけではない。
身を固めるまでの間だけ訪れる者もいる。
身代が崩れ、通えなくなった者もいる。
病に倒れた者。居を移した者。不意に客足が途絶える理由は客の数だけ有り、珍しい事ではない。新しい客が増えれば、馴染みだった客が顔を見せなくなる。
華やかな分だけ闇もまた深い。
いちいち、誰がどうなったかなどその後の行方を気にする者などいない。
まして、あの頃は変革の風が誰をも巻き込む勢いで吹き荒れていた。そのただ中にあの人は居たのだから、足が遠のいたとしてもなんら不思議は無い。
刀を常に腰に差し、その刃で人の命を絶つことに躊躇いも持たなかった人。
人を殺す者はいつか誰かに殺されるのが運命(さだめ)さ。
そう言っていたのは遊女仲間だったか、飯炊きの女だったか。あの人と同じ武士が言った言葉だったか。
あの人がどれほどの腕の持ち主なのかは知ることは無かった。
ただ、相当腕が立つという事だけは、噂に聞いていた。だから、そう簡単には敵の刃に倒れることは無いだろうと思って居た。それでも、人の運命はどうなるか判らない。一寸先は闇なのだから。その事は誰に言われなくても女郎にまで身を落とした自分がよく知っている。
だから、どんなに腕が立つと言われていても、けして斃れない訳ではない。
どこかの路地裏でその浅葱の衣を己の血に染めて、人知れず倒れ伏してしまったのかもしれない。だから、ここへ来れなくなったのだ
自分への関心が薄れたのではなく、ただ、この世に存在しなくなっただけ・・・
あの当時、まるで言い聞かせるように幾度もそう呟いたものだった。
女はあの頃の事を思いだし、口許にかすかに笑みを浮かべる。
なんだかんだ理由をつけつつも、その全てが当てはまらないことなど判っていた。
あの人が斃れれば、幾ら島原の外の話とは言え耳に入ってきただろう。だが、そんな噂話はただの一度たりとも聞こえて来ることなく、あの人の仲間は定期的に、楽しげな姿を見せていた。
夜ごと提灯の明かりに照らされて浮かび上がる浅葱の衣を見かけては、あの人が久しぶりに来てくれたのかと胸を高鳴らせて呼ばれるのを待っていた。
幾夜も・・・・・・
なぜ、そんな想いを男に抱くようになったのか女には判らない。
甘い睦言を呟いてくれる男も、貢ぎ物をしてくれる男も、足繁く通ってくれる男もたくさんいたにも関わらず、なぜ、その男一人に惹かれてしまうのかが判らなかった。
ただ判っていたことは、なぜとかどうしてとかそう言った理屈を抜きにして、ただ彼にどうしても惹かれてしまう自分がいて、再び自分の元に姿を現してくれるのを待ちわびる焦燥感に駆られてしまうということ。
忙しいとしばらく足を向けてくれなかった事は過去にもあった。
きっと、今回もそれが少し長引いているだけ・・・あり得ないと判っている。
それでも、万に一つの可能性を捨てきる事は出来ず、月が昇り沈んでいくのを、格子窓から見上げ、ため息を零す。
一度でいいから、共に朝を迎えて見たかった・・・・
女は、大門で男を見送る女郎仲間を見下ろしながら、誰かから聞いた唄を口ずさむ。
それはほんの数語で終わってしまう都々逸(どどいつ)。
共に朝を迎えられるのなら、世界中の鴉を殺してしまいたい・・・そんな唄。
『鴉? 朝を告げるのは鶏じゃありんせん?』
誰かがその唄を聞いたとたん、訝しげな顔をして首を傾げていた。
誰がどんな意味を込めて唄ったのかは知らない。
だが、とても短い・・・あっけない程すぐに終わってしまうこの唄を女は忘れる事は出来なかった。
空を飛ぶ鴉を見上げ、女は手を伸ばす。
鳥のように自由に空を翔る事が出来るのならば、今すぐにでもあの人の元へ飛び立ちたい。
だが、この身は借金という名の鎖に繋がれ、遊郭(しまばら)という檻から外に出ることなど許されない。
今まで何かを望んだ事など一度もない。
望みを持てば、叶わなかったときの絶望感が、より強くなる。
己の身に課せられた理不尽さに発狂したくなるから。
だから、何かを望むことなど今まで一度もなかったのに・・・
どうして、たった一時を共に過ごした男の事が忘れられないのだろう。
どうして、ここまで自分は囚われているのに、あの人はここへ来てくれないのだろう。
どれほど切望しても、ふつりと途絶えた足取りは再開される事は無かった。
一度遠のいた客足が戻ることはまずない。
そう判っていても、また来てくれるのではないかと、希望を捨てる事ができなかった。
例え、再び訪れてくれたとしても、自分とあの人の立場は何も変わらず、その距離が縮まることなどけしてないと判っていても・・・・
己の身をかがみみれば、そんな夢を見る方が愚かだと人は嘲笑うだろう。
それはけして手の届かない天にある月に、触れてみたいと望むようなものだ。
手を伸ばせば触れられそうで・・・だが、けして手が届くことはない。
どれほど背を伸ばし、台を使って身を伸ばそうとも。望めば望むほど飢(かつ)え、身を焦がし、己を追いつめてゆくだけだと。
女郎に心などいらない。
そんな物があると辛くなるだけだ。
そして、この身を惨めに思うだけだ。
判っていても・・・捨てたはずの心は、彼の人を求め、幾夜も幾夜も格子越しに彼の人の姿を求めていた。
やっと得ることが出来た自由の身になっても、今もなお、浅葱の衣を纏った闇のような人を探し求めている。
遊郭(しまばら)という檻から抜け出られても、浅葱の衣に自ら囚われて、けして自由になることは出来ない・・・いや、望んでいないと言うべきだろうか。
「あの方が、わちきの事を覚えていはるとは思えぬというに」
女は空を見上げたまま呟く。
あれから、幾年月が流れただろうか。
女にとっては昨夜別れたかのように、記憶に鮮明に残っているが、最後にその後ろ姿を見送ってから、もう幾度季節が巡っただろう。
その間に二百数十年日本という国を支配していた幕府は倒れ、新政府が日本を治めるようになり、追われていた者が追う立場になり、財を持っていた者が無くし、貧しき者が財を成す。
全てが目まぐるしく変わり果てていく中、自分だけが変われずにいる。
いや、むろん何も変わってないわけではない。
前は自由は何一つなかった。
だが、今は自由がある。
この足でどこまでも行くことが出来る。
だから、会いに行こう。
覚えていてくれるか判らない。
会ってどうしたいのか、自分でも判らない。
ただ、どうしても会いたかった。
今まで幾人もの、数え切れないほどの男と床を共にした。
その中には確かにいい仲になりかけた者もいた。
だが、それでもたった一人の人が住み着いて離れることはなかった。
一人の男に心を奪われるなど、女郎失格だ。
判っていても、想いはどうしようもなかった。
例え、想いが届かなくてもいい。
ただ、どうしても一度・・・たった一度で良いから、朝を共に迎えて欲しい。
「三千世界の鴉を殺し 主と朝寝がしてみたい 」
女は今にもかき消えてしまいそうなほど微かな声で、唄を呟くと、己の両手を見つめると口許を微かに歪め、ゆっくりと歩き出す。
第一章
会津の地から斗南へ移ってきて月日は瞬く間に過ぎさり、短かった夏が終わりを迎え冬がいつの間にか目前にまで迫っていた。
朝起きてみれば霜がすでに降り、吐き出す呼気は白く棚引く。
陽が山の連なりから姿を現し、霜を溶かしてくれたとしても、夏のような強い日差しはもうそこにはない。少しずつ温もりを無くしていく陽射しは、昼日中(ひるひなか)でもひんやりと寒気を感じる程までになっていた。
時折吹く冷たい風に、身震いをし実感せざるえない。
厳しいと言われる冬が間近に迫っているのだ。
千鶴は水桶から手を出すとゆっくりと自分の吐息を吹きかけて、悴んで感覚のない手を温めようとするが、その程度で温もりが戻るわけがない。
白い指先は真っ赤に染まり、自分の身体の一部とは思えないほど思うとおりに動かすことが出来なかった。
井戸水は通年通して温度は変わらないと言われるが、さすがに夏と冬では多少なりとも温度が変わる。少なくとも外気温の差が、こうして水仕事をしていると否応なく浸食し、体温を容赦なく奪ってゆく。
京や江戸の冬も深々と冷えこんだ。
水仕事をすれば悴み皹(あかぎれ)をこさえのが普通で、北国だから出来るというものでもない。北国ではなくても、水仕事をやれば誰もが当たり前のようにこさえていたものだ。
この斗南へ来る前には、豪雪地帯として有名な会津の冬も経験している。会津の冷え込みは、京や江戸とは比べものにならないほど厳しかった。
冬になれば雪に閉ざされ、里と里の行き来さえままらなかった。冬を迎える前に籠もる準備をせねば、春を迎えることは困難だ。雪に閉ざされる地域の生活は予想が付く。
だから、物資面はともかく、斗南へ来ても会津と大きな差はないと思って居たが・・・
「会津よりも、やっぱり冬は早いよね・・・」
改めて実感するまでもない。
斗南の土地は会津からはさらに北に進み、海を隔てた向こうには土方が命を散らせた蝦夷がある。今まで暮らしてきた地とは比べものになるはずがない。
一年の半分が冬だとも言われるような、厳しい土地。
この土地に移り住んできたのは水無月の終わりの頃。
既に四ヶ月以上この地に滞在し、なんとかその日を過ごして行けるだけの生活を送ってきたが、基盤が十分に整ったとは言い難い。
これから迎える冬を目前にしてどの程度薪を用意しておけばよいのか。どの程度食料を保存しておけば良いのか、皆目検討がつかなかった。
いや、例え必要な物が判ったとしても、十分に準備出来るほどこの土地は物がない。
あまりにも物が少なく、思うとおり冬支度さえ進まない。
それは千鶴だけに当てはまる問題ではない。
この土地に移り住んできた会津藩の者全員が、同じ問題に直面していた。
どうにかその日を食いつないで行くのがやっとで、一ヶ月先の事を・・・いや、一週間先の事を考える余裕すらない。それどころか今日の食事に欠く家の方が多く、千鶴とて十分満足するほどの食事を取れない日々が続くこともあった。
それでも、この地に来たことは一度も後悔はしていない。
もう二度と離れたくなくて。
どうしても一緒に居たくて。
ただ、傍に居られればそれで良かったから・・・だから、不毛と呼ばれるこの地へ共に来た。
あの日、謹慎から明けて一年半ぶりに再会を果たすことが出来た斎藤に、共に斗南へ行かないか?と誘われたとき、迷うことなく共に行くことを選んだ。
そう。迷うことなど一瞬たりとも無かった。
共にあれるのならばそれでいい。
それ以上望むことは何もない。
今もそう思って居る。
あの人の気配を感じ、あの人の声を聞き、共に食事をし共に休む。
穏やかで心地よい時間。
会話が多く交わされるわけではないが、囲炉裏を挟んで過ごす、静かな時間がとても心地よかった。
彼が話してくれる話に耳を傾け、自分の話に耳を傾けてくれる。微かに笑みをうかべ
その時浮かべられる穏やかな表情は、再会をするまで見ることなどほとんどなかった。京にいた頃も、江戸にいた頃も、会津にいた頃も・・・
京にいた頃はまだ平穏な時もあったが、やはり平隊士達もいる前で、三番組の組長たる斎藤が穏やかな雰囲気を出す訳にはいかなかったのか。それとも、そのような心境になることがなかったのかは判らない。
ただ、今思い返せば一番穏やかで、新選組が活気に満ちていた頃でさえ、今見るような穏やかな、優しい微笑を浮かべてるとこなど見かけた事はなかった。
むろん、今とあの頃では比べることは出来ない。
自分と斎藤の関係や築いてきたものが違いすぎる。
比較する方が無理だ。
ただ、それでも・・・少なくとも、今この時を穏やかに過ごして貰えるなら、千鶴はそれで満足でそれ以上の望みなどない。
確かにそう思って居るのに・・・不意に思ってしまう。
本当に自分は彼と共にこの地へ来て良かったのだろうかと。
洗い終えた洗濯物を出来るだけきつく絞って水気をはらうと、洗濯物を一つ一つ丁寧に干していく。
あと幾日こうして洗濯物を干せることが出来るだろうか。
今でも冷え込みが強いときは洗濯物が凍ってしまう。もう幾日もしないうちに外に干せるような気温ではなくなってしまうのだろう。
千鶴は悴んで思うとおりに動かせない指先に息を吹きかけながら、テキパキと洗濯物を干していく。
夏のように何処までも澄み切った空は、もう上天にはない。
秋の空とも違い、どことなく寂しげに見えるのは気のせいか、それとも気分の問題か。
洗濯物が凍るほど冷え込む季節になれば、空はどんよりとした重い雲に覆われて、辺りは一面白銀の世界になるのだろう。
この地はどの地よりも冬が早く、春が遅いと言われている。
ひとたび雪に閉ざされれば、自由に出入りはできなくなり、ただひたすら春の訪れを待つしかない。
それは何もこの土地だけではない。豪雪地帯の会津も同様だ。どんな生活になるか想像は付いているから、覚悟は出来ている。
だが、この土地は会津とも京や江戸とも違いすぎていた。
比較出来ない程、何もない未開の地。
生命線とも言える畑や田の開墾は捗っていない。
そもそも、この地に移住をし始めたのは水無月になった頃だ。それから数ヶ月過ぎたからといって、田畑の開墾が行われ、越冬するのに十分な食料をまかなえる程時間は経っていない。
今まで自分が経験したことが無いほど厳しい冬になるだろう。
覚悟はしている。餓えに苦しむことも、寒さに悴むことも。
だが、どうしても思わずにはいられない。
斎藤と共に居ていいのだろうか・・・・と。
幾ら、斎藤が誘ってくれたとはいえ、安易について来るべきではなかったのではないかと思うときがある。
この地はあまりにも不毛で、不毛故に色々と斎藤に苦労を掛けている。
自分が居なければ幾分かは楽だったのでは無いかと。
むろん、自分が居なくても生活が苦しいのは変わらない。
そんなことは判っている。
それでも、考える事をやめられない。
「今もまだ土方さんの命令を守っているだけなのかな 」
そう呟いたあと、千鶴は否定をするように首を激しく左右に振る。
そんな事は無い。
確かに土方から命じられたのが始まりだったかもしれない。
だが、今は確かに想いは通じ合っている。
疑う余地など何処にもない。
無口な人で、自分の想いをそう多くは語ってくれない人だが、それでも確かに自分の抱く想いは彼に届き、彼の想いは自分に届いている。
互いに惹かれ会い、共にいつまでも在りたいと・・・・
それでも、馬鹿な考えに囚われるのは何一つ関係が変わらないからだろう。
そう何一つ変わらない。
確かに、京にいた頃よりも、江戸に移った後よりも距離は縮まっているのは判っている。それでも、二人の間に確かなものは何一つ無かった。
将来を誓い合ったわけでもなければ・・・・
「ああ、もう! ただ、一緒にいられればそれで十分!」
傍にいられればそれ以上は望まない。
土方達と袂を分かち、斎藤が謹慎生活を余儀なくされ、一人その帰りを待つ時に願ったはずだ。
ただ、一緒にいられればそれ以上は何も望まないと。
それ以上を望んだら罰が当たる。
「洗濯物も終わったし、薪を集めに裏山に行ってこなきゃ」
こんな良い天気だというのに、しゃがみ込んでちんたら洗濯物などしているから、ろくな事を考えないのだ。身体を動かして働いていれば、そんな下らないことに囚われずに済む。
斎藤が、ただ己に課せられた役目だけに、自分と共にあるのではないかと・・・
そんな事を考える方が愚かだというのに。
今まで過ごしてきた時間が、ただ義務感と責任感だけでは無いことは十分に判っている。下らないことを考え過ぎていることも。
うじうじと考え込むのは好きではない。
自分達は思い合って共にいる。
それ以上でも以下でもない。
それで十分ではないか。
千鶴は泥沼に陥りそうになる思考を吹き払うように、氷のように冷たくなった両手で頬を強く叩くと、背後からきょとんとした声が届く。